春に田植えを終えると、いよいよ本格的なお米作りのシーズンが始まります。特に棚田のような特殊な環境では、水の管理や草刈りなど、細かい作業がとても重要です
今回は、田植え後に行う「溝切り」や「中干し」、その後の「水張り」、そして欠かせない「畔(あぜ)の草刈り」などについて紹介します。農作業に不慣れな僕たちにとっては、少し大変な作業ばかりですが、それぞれの工程の意味や効果を理解しながら、棚田オーナーとしての活動をお伝えしていきます

溝切り作業から始まる夏の管理

田植え後しばらくして苗が根付くと、「溝切り(みぞきり)」という作業を行います。これは、田んぼに浅い溝を掘って排水性を高め、中干しに備えるための大切な準備作業です
昨年も体験しましたが、原付バイクのような乗り物に乗って稲の間を走る作業です。一見楽しそうに見えるのですが、実はしっかり座っているわけではなく、軽く腰を浮かせた状態で乗るため、股関節にかなりの負荷がかかり、まるでトレーニングのようです!
上の写真は昨年の作業の様子です。今年は雨の中での作業だった為ビチョビチョになりましたが、その分、涼しい作業でした👍
● 溝切りの目的と効果
- 排水を促す:水を抜いた際、全体に水が滞りなく抜けるようにする
- 土壌の乾燥ムラをなくす:水が滞りやすい場所を減らし、均等に中干しできる
- 後の中干し・再灌水がスムーズに
棚田は傾斜地に作られるため、どうしても水がたまりやすい場所が出てきます。溝切りによって水の流れをコントロールし、全体の管理をしやすくしておくことが良い米作りの第一歩になります
中干し作業|稲を丈夫に育てるための大事な工程

溝切りが終わった後、田んぼの水を完全に抜き「中干し」と呼ばれる土壌の乾燥作業に入ります。田植えから1ヶ月ほど後の6月下旬~7月上旬に行うことが多いようです
あれだけユルかった地もすっかり固くなり、踏んでも全然沈まなくなりました👍
● 中干しの目的
- 稲の根を強く深く張らせる
乾いた土を求めて、根が地中深くまで伸びるようになります - 土中のガス抜き・病気予防
ぬかるんだ田んぼにはメタンガスなどが発生しやすく、根腐れの原因にも。中干しで酸素を入れて健全な土壌に保ちます - 無駄な分けつ(芽)の抑制
茎が増えすぎると栄養が分散し、穂が充実しにくくなります。中干しで育成をコントロールします - 地耐力を回復させ、収穫時にコンバインが沈まないようにする

こちらはもち米を植えた田んぼ。少し日影になる場所なので他と比べて土の乾き具合がゆっくりです
● 中干しの工程

- 田んぼの水を完全に抜く
- 自然乾燥で田面(たづら)をしっかり乾かす
- ひび割れが入る程度まで干す(10~14日が目安)
- 稲がしおれてきたら軽く水を入れ、再び乾かす「間断かんがい」で調整
棚田では平地に比べて乾きにくい場所もあるため、状況をよく見ながら部分的に排水口を開閉したり、補助的に水路からの排水も活用します
水張り再開|稲の最終成長を支える

中干しが終わったら、再び田んぼに水を張る「再灌水(さいかんすい)」を行います。この工程は出穂(しゅっすい=穂が出る)に向けた大切な成長の後押しとなります
● 水張り再開の目的と効果
- 稲の生育を再び促進させる
乾燥期間で抑えていた成長を再び活性化させます - 登熟(とうじゅく)を助ける
穂が出て実が詰まっていく過程で、安定した水の供給が必要になります - 気温の上昇から稲を守る
盛夏の暑さを和らげ、株元の温度を適度に保ちます - 雑草の抑制
水を張ることで酸素の少ない環境となり、発芽してしまった雑草の生育を防ぎます

● 再灌水の工程
- 水口(みなくち)から少しずつ水を入れ、田んぼ全体を均等に潤す
- 土が完全に湿ってから、通常の水位に戻す
- 出穂期まで安定した水管理を続ける
ここの棚田では水の管理は全てお師匠さんがやってくれています。なので我々は草刈りを全力で行ってお師匠さんをサポートしています

田植えから2ヵ月弱でここまで大きく生長してくれました。今年の関西は梅雨の時期が短かったので水張が出来るか心配でしたが、いいタイミングで雨も降ってくれました!

出来るだけ今の内にヒエなどの雑草は抜いておくのですが、この『クサムネ』が多過ぎて大変です!!稲刈りの時に一緒に刈り取られると玄米に黒い種子が混じるので、コレも少しずつでも駆除していかないといけません!!
耕作放棄地だった田んぼは色々な雑草の種が植わっている為にいっぱい雑草が生えてくるので大変ですが土の養分も豊富に蓄えているのか稲の成長も早いです
畔の草刈り|景観と病害虫の防止に不可欠な作業

見落とされがちですが、「畔の草刈り」は棚田農業において非常に重要な作業です。定期的に行うことで、田んぼの健全さと美しさを守ることができます
● 草刈りの目的
- 病害虫の発生を防ぐ
雑草が繁茂すると、カメムシやイナゴなどの害虫の温床になります - 水漏れ・畔崩れの防止
草の根が伸びすぎると畔の土が緩み、水が漏れる原因になります - 田んぼ周辺の視認性を高める
水位調整や農作業の際、見通しが良くなることで作業効率がアップします - 地域の美観維持
棚田の景観は観光資源にもなるため、草刈りは地域の誇りを守る作業でもあります
● 草刈りの頻度とタイミング

- 6月〜9月にかけて、月2回程度
- 中干し開始前、出穂期、収穫前など節目で行うと効果的
- 夏場は作業時間をいつもより1時間早めての草刈り
草刈りは地味で体力のいる作業ですが、棚田を守るうえでは欠かせません。他のオーナーさんたちと力を合わせて草刈りを行うので2時間程の作業で結構キレイにすっきりします!ただ本当に暑い日は1時間半ほどで切り上げて、あとは木陰で談笑しています
まとめ|丁寧な管理が美味しいお米を育てる
田植え後の棚田は、ただ稲が育つのを待つだけではありません。中干しや再灌水、畔の草刈りといった地道な作業を一つ一つ丁寧に積み重ねることで、稲はたくましく育ち、美味しいお米を実らせてくれます
特に棚田は自然との距離が近く、水や土、生き物の営みにも配慮が必要な場所。手間はかかりますが、そのぶん育ったお米の味わいも格別です👍
里山の風景を守りながら、美味しいお米づくりを楽しむ。そんな棚田での農作業の魅力を、ぜひ多くの人に感じていただければと思います

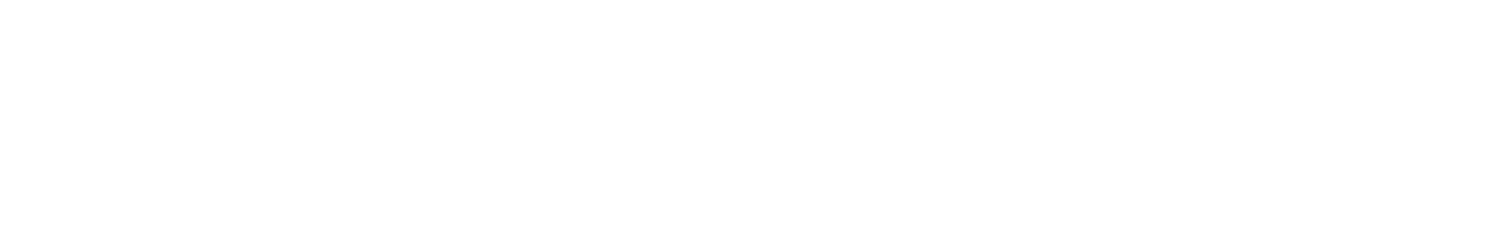

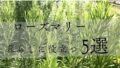

コメント