昨年から参加している棚田オーナー制度。昨今のお米価格の高騰を考えると何ともありがたいタイミングでした
そして2年目の今年は耕作放棄を復田してお米づくりをしていきます!
草がボーボーに生えてしまいとても半年ほどで田植えが出来る状態になるのかと思うほどでしたが、師匠の指示のもと少しずつ手入れを行い準備をしてきました。田植えの直前まで本当に間に合うのかと半信半疑でしたがとうとう田植えの季節を迎える事になりました

秋から始まる準備作業

お米作りと聞くと春や夏のイメージがありますが準備は前の年の秋から始まります。10月中旬から11月にかけて元気に生い茂っている雑草を刈るのですが数年放置されていた田は雑草もビッシリ生えているので2~3回に分けてしっかりと刈っていきます!

草刈りが終わり田んぼの現状があらわになりましたが水捌けがあまりよく無いようで一部は足を入れるとグニョグニョとしていて湿地帯のようでした!
少し土を乾かしてからトラクターを使って耕してもらったのですが、ぬかるみが酷い所は流石に入れまなかったようです。。

あとは手作業で少しずつ耕したり排水の為の溝をつくったりしていきます
水の流れを整える工夫

土を耕したあとは、田んぼの形を整えていきます。これまでの畦(あぜ)だけでは水の管理がうまくいかないこともあるため、田んぼの内側にもう一本、畦を新しく作ることになりました。これにより水が均等に行き渡るようになり育ちに差が出にくくなります。

冬の間に田んぼに一度水を張ってみます。こうすることでどこに水がたまりやすいかなどが確認できます。入水口と排水口があるのである程度は勾配をつけないといけないのですが溝を掘っているとドンドン深くなっていくので体がムッキムキになりそうです!
しかし体がバッキバキになったので終了しました(´;ω;`)

娘たちはオヤジを放ってヤギ小屋に去っていきました!
その後しばらく放置したのち、もう一度トラクターで土を起こし、より細かく整えていきます。この辺までくると大分と田んぼらしくなってきました。

そしてまた水をためたら、畦側に沿って溝を掘っていきます!掘ったり、盛ったり、崩したりと大変ですが本格的砂遊びみたいな感覚でちょっと楽しくなってきます

水漏れを防ぐ大事な作業

春が近づいたら土をさらにきめ細かくならしていく作業を行います。トラクターを使って土を混ぜることで、泥の状態に近づけます。この作業を「代掻き(しろかき)」と呼びますが、数年ぶりの耕作を行う田んぼなので通常よりも多くこの代掻きを行います
しかし田んぼに張った水が畦からチョロチョロ~と水漏れを起こしており水がしっかりとたまってくれません、、
原因はオケラなどの虫たちが畦にトンネルを掘っているようです、、しかたがないので水が染み出ているあたりの畦をスコップでザックザックと刺して中の穴を潰してから足で踏み固めていく作業を水漏れ箇所を確認しながら行っていきます

そして何度かトラクターで田を平らにしてもらいましたが、どうしても一部の土が高く盛り上がってしまうことがあります。そういう場所は、手でレーキを使って平らにしていきます。少し地道な作業ですがここで丁寧に整えることで苗の生育が揃いやすくなります。

いよいよ田植えの本番!

こうして準備が整ったら、5月上旬に田植えを行います。手作業や機械を使って苗を均等に植えていきます。お米作りというとこの田植えの場面を思い浮かべる方が多いかもしれませんが実はその前の準備がとても大切なんですね

復田した田は地がゆるいので師匠にお任せして、僕は隣の田んぼで田植え機の運転です
耕作放棄地を再生するのは手間も時間もかかりますが泥だらけになった分、愛着も出てきます。これから秋の収穫まで、まだまだ作業は続きますが自分の手で育てたお米を食べられる日が楽しみです
そして今年はもち米づくりにもチャレンジしております


他のオーナーさんたちと手作業で出来る範囲でやっています。ありがたい事に師匠が丁度いいサイズの田んぼを貸してくれたので収穫出来たらみんなでお餅つきを予定しています
田んぼオーナー制度に興味のある方はコチラの記事も覗いてみて下さい↓↓

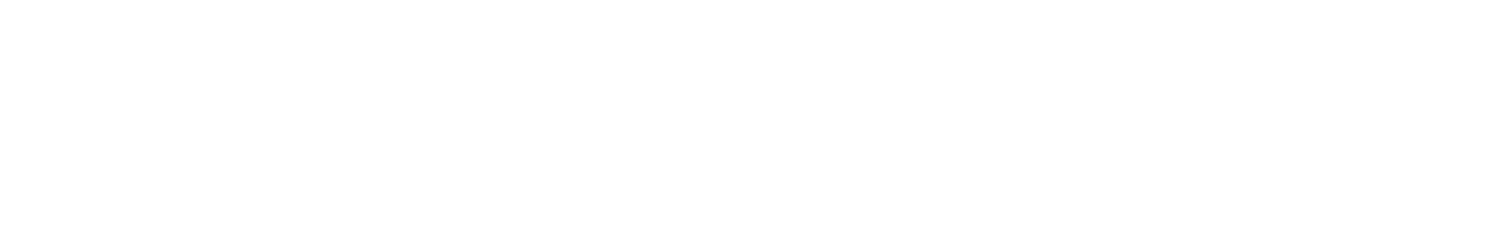



コメント